はじめに
こんにちは、みらいです。
2025年9月現在、金価格は連日で過去最高値を更新しています。
世界経済の先行き不透明感、インフレ懸念、株式市場の高騰リスクなどが背景にあり、多くの投資家が「守りの資産」として金に注目しています。
株式や債券は景気の影響を大きく受けますが、金はそれらとは異なる値動きをするため、分散投資の有効な手段となります。特に暴落対策やインフレヘッジとして、資産の一部に組み入れる投資家が増えています。
一方で、これから金投資を始めようとする方にとっては「どんな方法があるのか?」「少額からでもできるのか?」といった疑問も多いでしょう。
そこで本記事では、金投資の代表的な始め方を4つ(現物・ETF・投資信託・純金積立) に分けて徹底解説します。
1. 現物の金を買う(ゴールドバー・金貨)
もっともイメージしやすいのは「現物の金」を買う方法です。
田中貴金属や三菱マテリアルなど大手貴金属会社、または銀行経由で購入できます。
メリット
- 手元に実物がある安心感
- インフレや金融不安に強い(「究極の安全資産」)
- コレクションや贈答用にも活用可能
デメリット
- 保管に注意(盗難・火災リスク)
- 購入時・売却時に手数料やスプレッドがかかる
- 小額からの投資は難しい(1g単位は可能だが割高)
現物の金の投資のポイント
現物の金は、長い歴史の中で「どの国でも価値を認められる資産」として扱われてきました。
紙幣や株式と違い、国家や企業の信用に依存しないため、極端なインフレや金融危機のときでも価値を失いにくいのが特徴です。
特に戦争や政情不安などの「有事」には、安全資産として金の需要が高まり価格が上がる傾向があります。
一方で、実際に購入した場合は「どこに保管するか」が最大の課題です。
自宅で金庫に保管するケースもありますが、盗難や火災のリスクを考えるとセキュリティの高い貸金庫を利用する人も多いです。ただし、貸金庫には別途利用料がかかるため、実質的な保有コストが増える点は押さえておきたいポイントです。
👉 現物の金は「万一のときの資産防衛」として強力ですが、流動性や保管コストの課題もあるため、全体資産の一部に限定して持つのが現実的です。
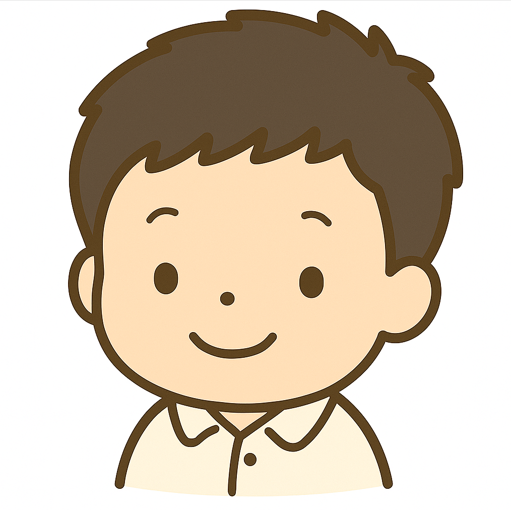 みらい
みらい僕も5年以上前に「金貨」を購入して大切に保管しています。金貨に関しては金の価格以上に値上がりしており当時の数倍の価値に値上がりしていました。
2. 金ETF(上場投資信託)
株式と同じように証券口座から売買できるのが「金ETF」です。
東京証券取引所に上場している「純金上場信託(1540)」などが代表例です。
ETFとは Exchange Traded Fund(上場投資信託) の略で、株式と同じように証券取引所で売買できる投資信託のことです。
メリット
- 株と同じように簡単に売買できる
- 信託報酬が低くコストが抑えられる
- 少額から投資可能
デメリット
- 実物の金を保有しているわけではない
- 配当や利息がつかない
金ETF投資のポイント
金ETFは、実際には信託銀行などが「現物の金」を保有していて、その価格に連動する形で値動きします。つまり、自分が直接金を持つわけではないものの、実物の金の値動きに手軽に投資できる仕組みです。
現物の金と違って、証券口座があればいつでも売買でき、売却しても現金化に時間がかかりません。たとえば「急にお金が必要になった」というときに、即日換金できるのは大きな利点です。
また、配当がないため「持っているだけではお金は増えない」という点も理解しておく必要があります。
👉 金ETFは「金の安心感」と「株式の流動性」のいいとこ取りができる商品ですが、あくまで投資口座の中での管理資産という位置づけになります。
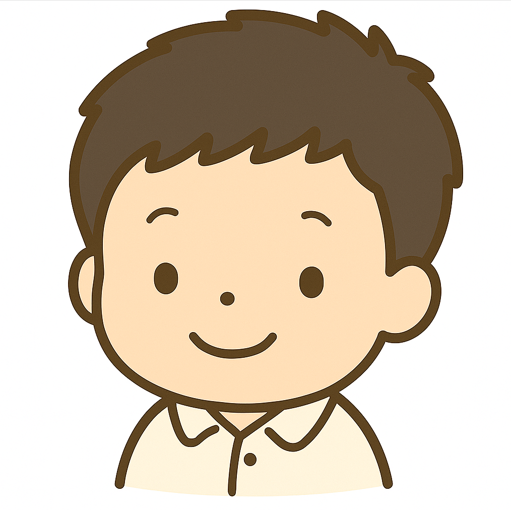
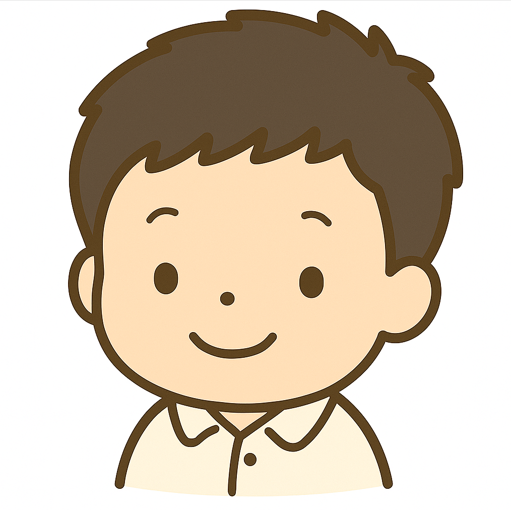
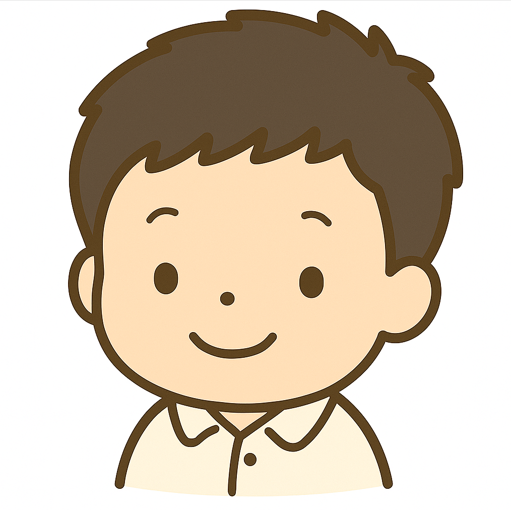
純金上場信託(1540)は僕も購入しています。配当金がないのでポートフォリオの一部で安全資産として持ち続けています。
3. 金の投資信託
金の価格に連動する投資信託もあります。
ETFに比べて手数料は高めですが、積立設定が簡単にできるのが特徴です。
メリット
- 100円など超少額から始められる
- NISAやiDeCoでも利用可能(長期投資向き)
- 自動積立ができる
デメリット
- 信託報酬がETFより高め
- 直接「現物の金」を保有しているわけではない
金の投資信託の投資のポイント
金の投資信託は、ETFに似ていますが「積立のしやすさ」に強みがあります。証券会社や銀行の口座から毎月自動で引き落とされる設定ができるため、投資を習慣化したい人にとっては便利な商品です。
NISAやiDeCoに対応している商品も多く、長期投資の枠組みの中で金を持てるのも大きなメリット。たとえば「株式インデックスファンド+金ファンド」を組み合わせて保有することで、株価下落時の資産防衛につながります。
ただし、投資信託はETFよりも信託報酬(運用管理費用)が高めです。数十年単位で積み立てると、運用コストが複利で効いてくるため、手数料の確認は欠かせません。
また、ETFと同様に「現物の金」を直接持っているわけではないため、有事の際の物理的な資産防衛力は劣ります。
👉 投資信託は、NISAやiDeCoを活用したい人・コツコツ積立が得意な人にとって現実的で始めやすい選択肢です。
4. 純金積立
毎月一定額をコツコツ積み立てる方法です。
田中貴金属や三菱マテリアル、楽天証券、SBI証券など多くの金融機関で利用できます。
メリット
- 1,000円〜など少額から積立可能
- 金価格が高いときは少なく、安いときは多く買える(ドルコスト平均法)
- 長期で自然に金を積み上げられる
デメリット
- 手数料(買付手数料や保管料)がかかる
- 短期での売買には不向き
純金積み立ての投資のポイント
純金積立は、証券会社や貴金属会社を通じて毎月少額から金を積み立てていく方法です。特に「ドルコスト平均法」の仕組みが自然に働くため、金価格が高いときは少なく、安いときは多く購入できるのが特徴です。
そのため、長期でコツコツ買い続けると価格変動リスクを平準化できるのが大きなメリットです。
さらに、純金積立は「最終的に現物を受け取れる」仕組みを持つサービスもあります。たとえば田中貴金属や三菱マテリアルでは、積み立てた金をゴールドバーや金貨として引き出すことも可能。これはETFや投資信託にはない魅力です。
一方で、純金積立は「手数料が割高」になりやすいのが難点です。買付手数料・保管料が数%かかることもあり、短期で売買すると手数料負けしてしまう可能性があります。したがって、10年以上の長期運用を前提に考えるのが基本です。
👉 純金積立は、コツコツ投資したい人・将来的に現物も選択肢に入れたい人に向いています。
その他 金鉱株・金鉱株ETF
金を採掘する企業の株式や、金鉱株を集めたETFに投資する方法です。
代表的なETFには「VanEck Gold Miners ETF(GDX)」などがあります。
👉「リスクを取ってリターンを狙いたい人」「株式投資に慣れている人」の投資商品です。
リスクとリターンを慎重に検討してから購入しましょう。
メリット
- 金価格上昇時に大きな値上がりが期待できる
- 株式市場で売買できる
デメリット
- 企業の経営状況や株式市場の影響も受けるため、金価格と完全に連動しない
- ボラティリティ(値動きの大きさ)が高い
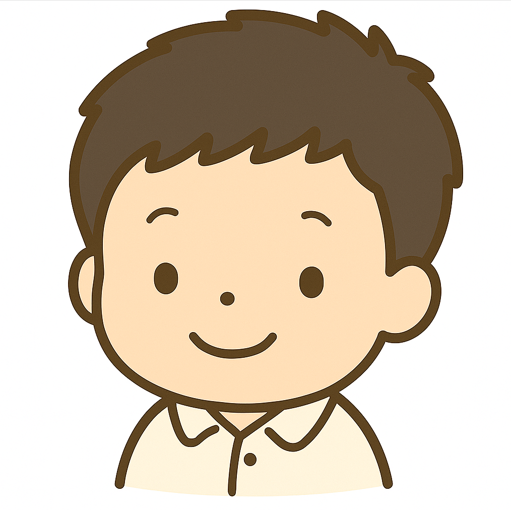
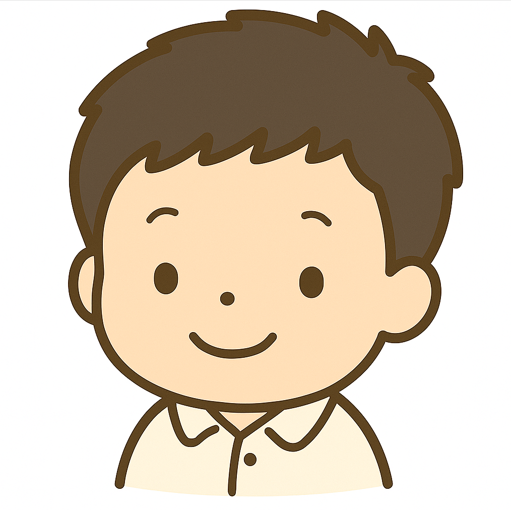
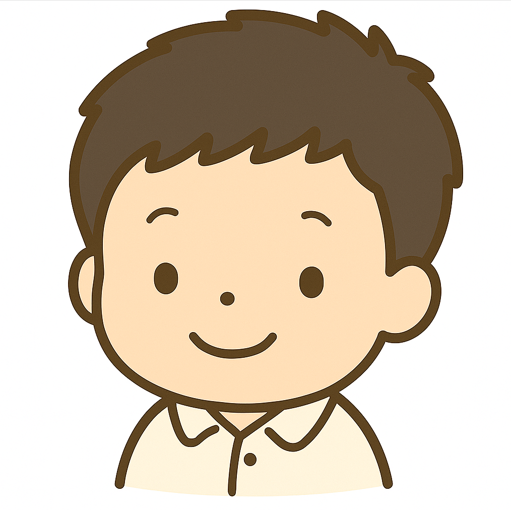
まずは現物・ETF・投資信託・純金積立といった基本的な方法から始めてみると、金投資に慣れていきやすいですよ。
金投資の注意点
金は「守りの資産」として有効ですが、注意点もあります。
・利息や配当がないため、長期資産形成には株や債券との組み合わせが重要
・投資方法ごとに手数料やスプレッドが異なるので、事前に確認が必要
・「全財産を金にする」のはリスクが高く、資産の一部(10〜20%程度)に分散して持つのが基本
まとめ 〜金は資産防衛の「保険」~
金は短期的に大きな利益を得るための投資ではなく、インフレや金融危機のときに資産を守る「保険」的存在です。
我が家でも、株式や債券を中心に運用しつつ、資産の一部を金に分散しています。
実物の安心感を持ちたいならゴールドバー、手軽さを重視するならETFや投資信託、コツコツ積み上げたいなら純金積立…と、自分のスタイルに合わせて選べるのが魅力です。
資産形成を考えるうえで、「金をどう取り入れるか」はリスク管理の大事な一歩になります。
最後に、別記事のご紹介で「金融危機や株価暴落に備えるためのリスク管理」についてもまとめています。
ぜひ参考にしてみてください。
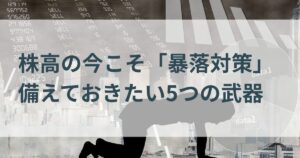
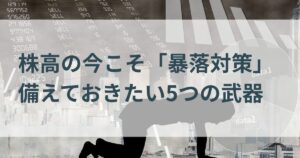
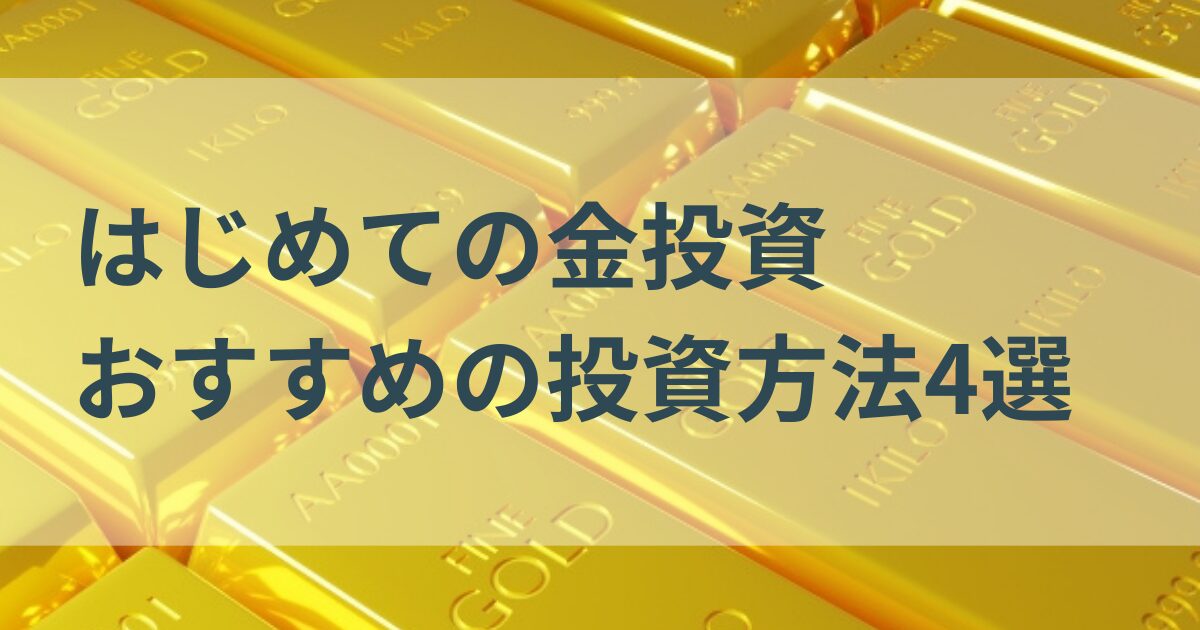
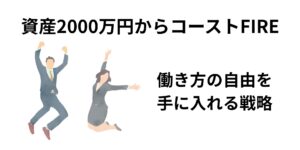
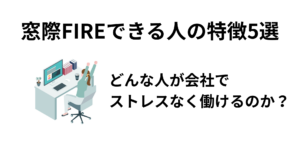
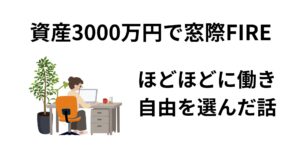
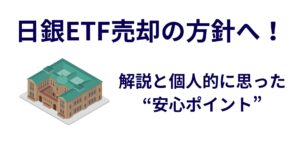

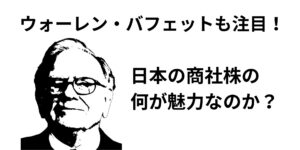
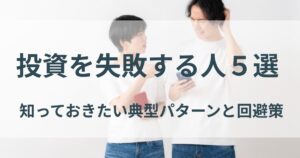
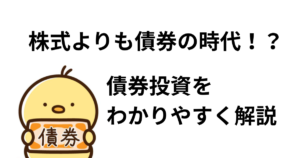
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] あわせて読みたい 【はじめての金投資】おすすめの投資方法4選!徹底解説 はじめに こんにちは、みらいです。2025年9月現在、金価格は連日で過去最高値を更新しています。世界経済 […]
[…] あわせて読みたい 【はじめての金投資】おすすめの投資方法4選!徹底解説 はじめに こんにちは、みらいです。2025年9月現在、金価格は連日で過去最高値を更新しています。世界経済 […]