金融庁が検討している2026年度の税制改正要望の概要が明らかになりました。
ポイントは、NISA(少額投資非課税制度)の対象を高齢者や子どもを含む全世代に拡大する方針です。
これにより「貯蓄から投資へ」の流れをさらに強め、家計全体での資産形成を後押しする狙いがあります。
税制改正の大きな柱
- NISAの対象を全世代に拡大
18歳未満も利用可能になれば、早期から資産形成が可能に。 - 高齢者向け商品も対象へ
毎月分配型の投資信託など、定期収入を得やすい商品が選べる。 - 暗号資産課税の見直し
ビットコインなど仮想通貨取引に関する税制も検討対象。
今後のスケジュール
- 8月末まで:金融庁が財務省に要望提出
- 年末まで:与党などと協議し具体案をまとめる
- 来年の通常国会:法案成立を目指す
最短で2026年から新制度がスタートする可能性があります。
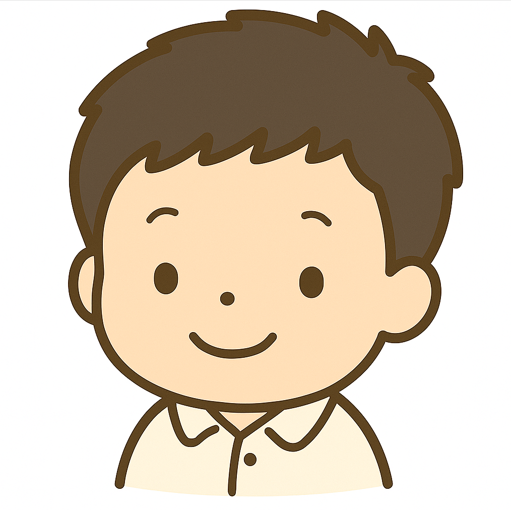 みらい
みらい現行制度だと、18歳以上しか使えず、投資できる商品も一部に限られています。新しい制度が始まれば、子どもから高齢者まで幅広い世代が活用できて、もっと自由に資産形成できるようになります!
世代別の投資シナリオ
子ども世代(未成年)
もし未成年もNISAが利用可能になれば、親が子どもの名義で積立を開始できます。
- 例:月1万円を18年間積立、年利4%で運用 → 約300万円に成長
- 学資保険の代替や、将来の教育費準備に活用できる
小さいころから投資に触れることで、金融リテラシー教育の一環にもなります。
働き盛り世代(20〜50代)
現役世代は、長期的な資産形成を目的に「つみたて投資枠」を活用するのが王道です。
- 株式や投資信託で20年以上積み立てると、複利の効果が大きく働く
- 例:月3万円を20年積立、年利5%で運用 → 約1,200万円に成長
老後資金や住宅資金、教育資金など、将来のライフイベントに備えるために有効です。
高齢世代(シニア層)
年金生活に入る世代は「資産を増やす」より「資産を守りながら取り崩す」ことが大切です。
- 毎月分配型の投資信託を利用 → 定期的な収入を確保
- 生活費を補う“第二の年金”として機能
- ただし、元本切り崩しのリスクがあるため注意が必要
「老後も投資で収入を得られる」という安心感につながります。
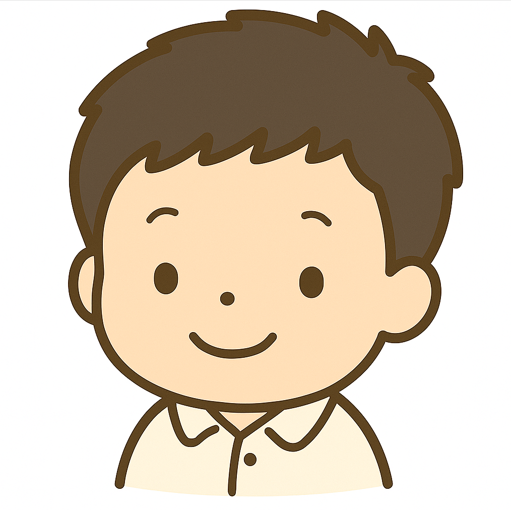
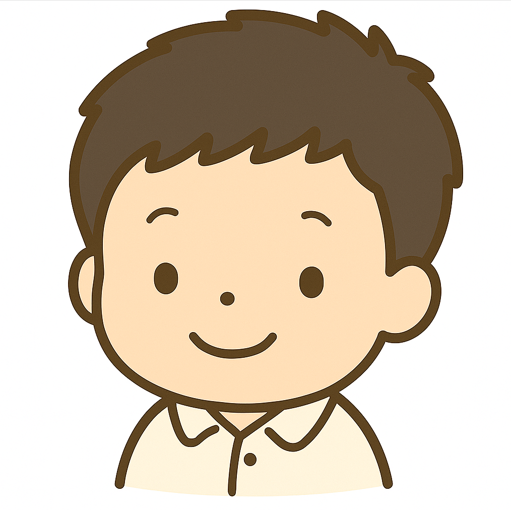
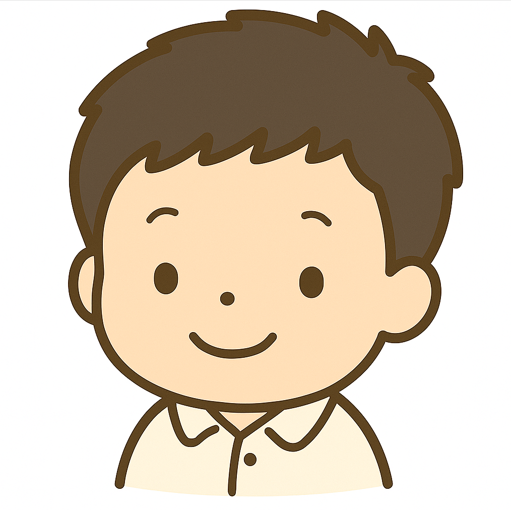
NISAで投資できる商品が増えて、幅広い世代が自由に投資できるようになったら、投資判断はこれまで以上に慎重に行うことが大切ですね。
家計への影響
今回の見直しで、NISAはライフステージごとに次のような役割を担う可能性があります。
- 子ども世代:教育資金・投資教育の第一歩
- 働き盛り世代:長期積立で資産形成の中心
- 高齢世代:生活資金を補う安定収入源
世代を超えて投資文化が根付くことが期待されます。
まとめ
金融庁の税制改正要望によって、NISAは「一部の世代が利用する制度」から「誰もが使える制度」へと進化する見込みです。
子どもから高齢者まで、幅広い世代がライフステージに応じた資産形成を進められるようになるかもしれません。
ただし、投資にはリスクがつきものです。
「NISAなら必ず儲かる」というものではないため、自分の資産状況やライフプランに合わせて活用することが大切です。
出典
本記事は、Yahoo!ニュースの記事を参考に作成しました。
NISA、全世代対象に拡大へ 金融庁が税制改正要望 (2025年8月26日配信)

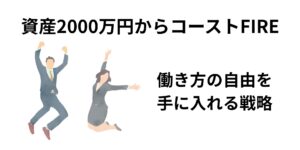
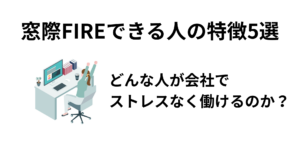
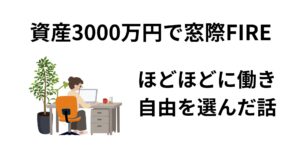
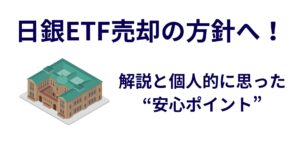

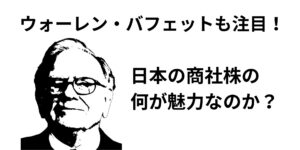
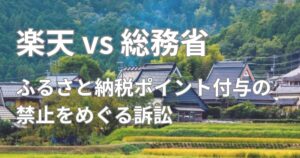
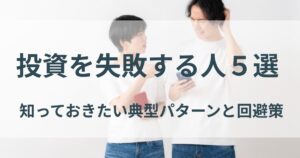
コメント